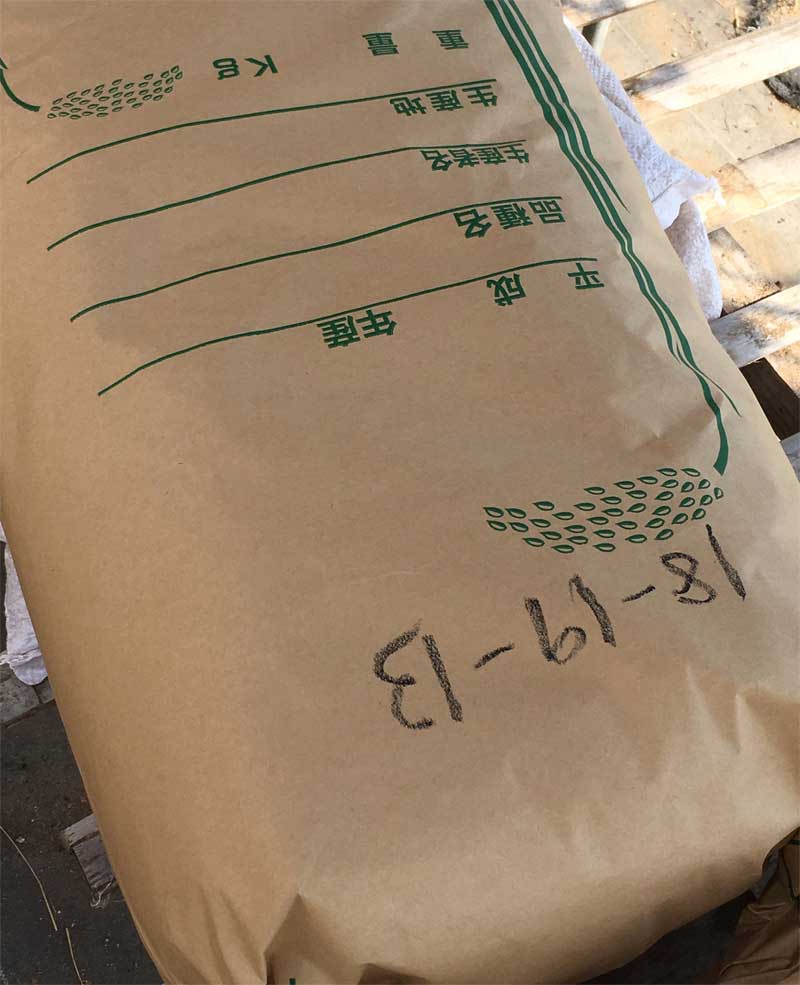三寒四温とはよく言ったもので、一気に暖かくなりそうな予感を感じさせたこの春も、気温が上がった翌日、また冬のような寒さに逆戻りという日を何度か繰り返している。
それでも天気予報で来週は気温が上がると言っているので、急に本格的な春が訪れるのかもしれない。
毎年、春らしい陽気を感じて慌てて「あ~、冬の間に◯◯を終えてなかった!」と反省するのだが、今年はどうなるのだろうか。
今、ビニールハウスの中でも、冬越しした、寒さに弱い苗のメンテナンスが進んでいる。レモングラスなど、成長はしないのだが、ポット苗にはいつの間にか雑草が生え、いち早く大きくなりつつある。今後は更に急激に成長するだろうから、今のうちに草取りをしたり、土を入れ替えたりする作業が必要だ。
そんな作業中のスタッフが、「いつもベチバーをかじる芋虫がもう動いている」と教えてくれた。ベチバーの葉の縁をギザギザに噛んで食べる芋虫だ。

やわらかく青々と太った姿は、冬の間もずっとかじっていたのではないかと思えるぐらい。
ただ、種類は何かがよく分からない。手に乗せてみると、クルッと丸まった姿が、夜盗虫に似ていたので、「夜盗虫じゃないの?」と話していた。芋虫、毛虫の類は同じ種類でも成長具合によってずいぶん色や形が変わる。◯齢幼虫という姿まではとても把握できない。そもそも覚える気力も、覚えるための脳のスペースも減る一方なのだ。

ただ、後になって、なんでも食べそうなヨトウムシとはいえ、イネ科のベチバーまで食べるのだろうか?いや、食べるものがなければ食べるだろう・・・。でも、妙に特徴のある顔をしていたな・・・と、妙に気になっていた。
午後、ちょっと時間が空いたので、ネットで調べてみることにした。こういう時頼りになるのが「幼虫図鑑」。この手の芋虫、毛虫嫌いの人は見ないほうが良いサイトである。大抵の芋虫や毛虫はこれで見つけることができるが、今回はなかなかヒットしない。
雰囲気が似ているヨトウムシの仲間、スズメガやシャチホコガの仲間などを見てみるが、どうしても見つからない。
そこで、考え方を変えてみて、食草から当たってみることにした。一旦このサイトから離れて、「イネ科 イモムシ 幼虫」で画像検索してみると、見事同じ顔つきのイモムシを発見。どうやらチャバネセセリの幼虫だったようだ。成虫は花の蜜を吸うそうなので、花が咲き始める頃には成虫になっているのかもしれない。

それにしても、暖かくて、外敵もあまりいなくて、食べ物が豊富なビニールハウスの中という、卵を産み付けるには最適の環境を見つける力には脱帽せざるを得ない。
後ほど、「幼虫図鑑」でも「チャバネセセリ」を調べてみたらきちんと載っていた。探し方が悪かったのだろう。