一年も1/4が終わってしまった・・・。
明日から4月というのに、今日は冷たい雨。ようやく今週あたりから暖かくなって苗たちにも成長の兆しが見えてきたのだが。

「○○はいつごろできますか?」といったお客様からのお問い合わせも増えてくる季節。空を見てはもどかしさを感じてばかりいる。
先日も雪で壊れたビニールハウスの立て直しに取り掛かったのだが、天気予報が見事に外れて作業が何度も中断。半日で終わるつもりの作業が丸一日かかっても完了できなかった。
とはいえ、空をにらんでみてもどうにもならない。こんなとき思い出すのが「湖山長者」という昔話だ。
もともと、お隣の鳥取県に伝わる民話なので、子供の頃「山陰の民話」とかいうような本で読んで覚えていたのかもしれない。詳しくは下記リンクで読んでもらいたいのだが、一言で言えば、「自然は思い通りにはならないし、自然に対して傲慢になるとひどいしっぺ返しを食う」という戒めである。きっと全国各地にも似たような民話があるのだろう。
子供の頃に読んだ民話なんてほとんど覚えていないのに、なぜこの話を覚えているのかがそもそも不思議だ。
しかも、今になってこの教訓をいつも実感させられている・・・。
もうひとつ、よく覚えている話が、長者の娘の婿えらびに、山盛りの豆ご飯を食べさせるというお話。これは豆ご飯を食べる描写がとても美味しそうだったというだけなので、タイトルも覚えていないのだが・・・。
こちらもネットで探してみたが、それらしいものは見つからない。似たような内容の話は全国各地にあるようだけど。
———————————————-
さすがに気になったので、図書館で探してきた。新版になってはいたが、表紙も内容も、挿絵も昔のまま。とても懐かしかった。
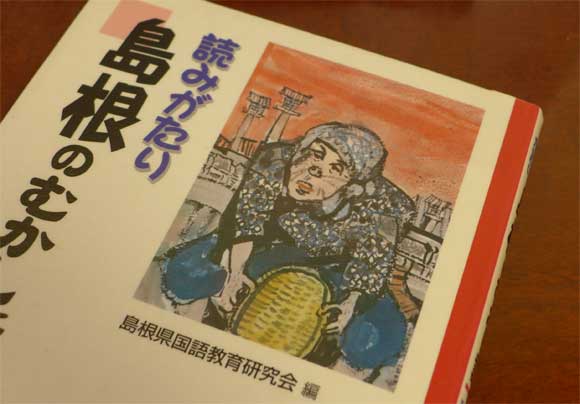
それにしても記憶は曖昧なものだ。豆ご飯ではなく粟(あわ)のご飯だった。でも、いま読んでもやっぱり美味しそうに思えたのが妙におかしかった。
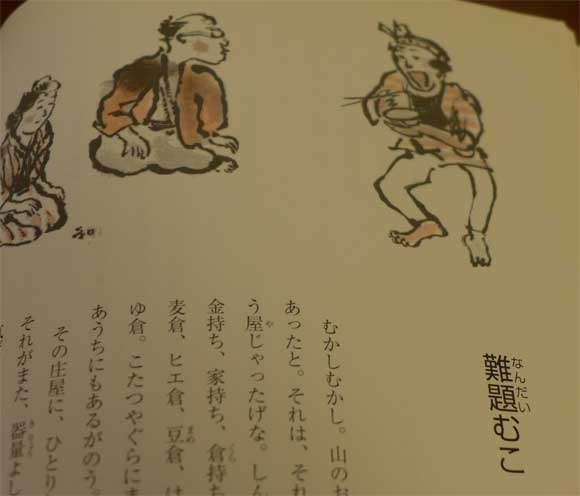
「湖山長者」
http://www.city.tottori.lg.jp/koyamaike/kg-1/kg-4/kg4-3/kg-4-3-koyamatyoujya.html
【民話】湖山長者














 大きくて見事なアップルゼラニウムの鉢植え。その隣に今回お送りしたまだちいさなアップルゼラニウム。
大きくて見事なアップルゼラニウムの鉢植え。その隣に今回お送りしたまだちいさなアップルゼラニウム。
 一方今年は1月から大雪が続いたせいもあるのか、赤も白も立春になっても全く咲く気配を見せず、3月に入ってから揃って咲きだす始末。今の所、むしろ白梅のほうが先行しているぐらいだ。
一方今年は1月から大雪が続いたせいもあるのか、赤も白も立春になっても全く咲く気配を見せず、3月に入ってから揃って咲きだす始末。今の所、むしろ白梅のほうが先行しているぐらいだ。







